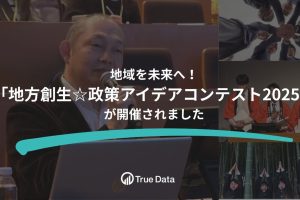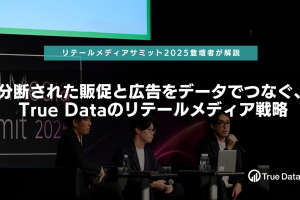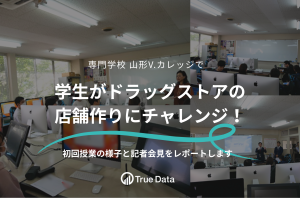こんにちは。流通気象コンサルタント・気象予報士の常盤勝美です。皆さんはワインはお好きですか。私は飲む機会はそれほど多くなく、また料理によって赤白飲み分けるほどではないのですが、ワインは赤白とも好きです。今回は、赤ワインと白ワインの購入個数と気温の関係における違いについて考察してみました。
購買データを抽出した商品
弊社True Data の提供する購買データ分析ツール「Eagle Eye」から抽出した「果実酒カテゴリ」の商品のうち、直近1年の購入個数上位10商品の赤ワイン、白ワインをそれぞれ選定しました。なお今回、スパークリングワインは対象から外しています。
赤ワインと白ワインの購入個数と気温の関係


※購入個数は伏せていますが、それぞれ縦軸の目盛りは合わせています。
商品の購入個数と気温の関係を調べるため、図表1のように散布図を作成しました。散布図に示されている点(プロット)はほぼ横一線に配置されているように見えます。これは気温の上下による売上の変動幅が小さいことを示唆します。ちなみに、ビール類は気温が高いときに消費が多くなり、気温が低いときは相対的に少なくなるというように気温による売上の変動幅が大きい特徴があるので、ワインの気温の関係とは対照的です。
そして、この散布図を細かく見ると、両者ともわずかに右肩下がりの分布となっています。夏よりは冬の方が、わずかに購入個数が多い傾向にあるようです。
なお、両者とも12月に購入個数が多くなっていますが、気象条件以外にも、クリスマスの食卓向けという側面もありそうです。
売上と気温の関係、両者の違い
全赤ワイン、白ワイン、それぞれの散布図を見ると、両者に大きな違いはないようですが、詳しく見るとちょっとした違いがあり、そこに着目しました。赤ワインの方が、より高い温度帯(おおむね最高気温25℃以上)において、気温の上昇に伴う購入個数の減少幅が白ワインより大きくなっています(図表2)。一般に赤ワインは常温で、白ワインは冷やして飲むことが多いため、最高気温が25℃を超えて暑さを感じるときは、赤ワインより冷えたビール類や白ワインを選ぶ人が多く、この違いになったと考えられます。

まとめ
データを細かく分析すると、同じワインでも、種類の違いによって気温との微妙な関係性の違いがあることが確認できました。小売店舗であれば、売場を作ったり発注数量を決めたりする際の、メーカーであれば、商品開発や製造・出荷計画の参考にしていただければ幸いです。
※抽出データ 株式会社True Data「Eagle Eye」に搭載されている「果実酒」カテゴリ(業態:スーパーマーケット、期間:2023年5月1日~2025年4月27日、データ抽出日:2025年5月14日)のうち、赤ワイン、白ワインそれぞれ上位10商品(スパークリングワインは除く)の購入個数。
本ブログに対するご意見、ご感想、気象と消費データに関するお問い合わせ等は、お気軽にこちら(https://www.truedata.co.jp/contact)までお寄せください。

株式会社True Data 流通気象コンサルタント 常盤 勝美
〈プロフィール〉
大学で地球科学を学び、民間の気象会社で約20年にわたりウェザーマーチャンダイジング関連サービスに従事。2018年6月、True Dataへ入社し、気象データマーケティングを推進。著書に『だからアイスは25℃を超えるとよく売れる』(商業界)など。気象予報士、健康気象アドバイザー。