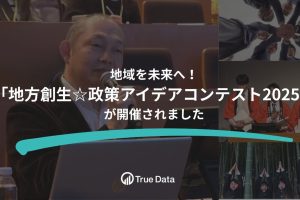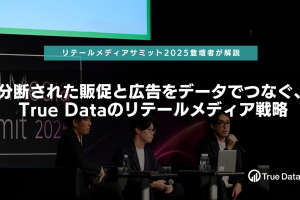こんにちは。流通気象コンサルタント・気象予報士の常盤勝美です。1年間にわたり主にメーカー企業の方に向けて執筆してきた、気象&購買データ活用法に関する連載は、今回(第12回)が最終回です。これまでの連載の内容のおさらいと本格的な地球沸騰化時代に向けて企業として取り組むべき事業継続における重要なポイントをご提案します。
取組の手順
気象庁のウェブサイト「気候リスク管理の解説ページ」にも記載されているとおり、異常気象や地球沸騰化などを含め気候リスクに対する取組は、次の3つのステップで考えるのが進めやすいでしょう。今回の連載でも、この3つのステップに沿って解説してきました。
- 気候リスクを認識する 第一回 「意外と知らない!?業務に使える気象データ3選」 第二回 「気象予報士が教える、長期予報の活用方法と行間の読み方」 第五回 「今後の日本の気候はどうなっていくのか?」 第六回 「大胆仮説!2050年の日本の天候」
- 気候リスクを評価する 第三回 「長期予報に基づく売上の予測値計算法」 第四回 「長期予報を活用したコストロスモデル」 第十回 「広告宣伝の効果と気象の影響の切り分け法」
- 気候リスクへ対応する 第七回 「異常気象に備えるための心得とは」 第八回 「ウェザーMDを利用した商品開発」 第九回 「商品前線の活用」 第十一回 「メーカーの取り組むべき天候リスクヘッジ」
気候変動に対するBCPの方向性
近年、「極端気象」(ゲリラ豪雨、猛烈な暑さ、干ばつなど)と呼ばれるように、気候変動の影響は地球規模で顕著になり、それに伴う自然災害がかつてないほど猛威を振るっています。これらの現象による災害は、従来のBCPでは想定しきれなかった新たなリスクを含んでいます。例えばサプライチェーンへの長期的な影響や、近年日本でも発生数が増加傾向にある広範囲の山火事などがこれに該当します。地球沸騰化時代に企業が事業継続性を確保するために、BCPをどのように見直し、強化すべきか、その方向性を簡潔に提示します。
- 気候変動シナリオの活用:IPCCの報告書などを参考に、将来起こりうる気候変動シナリオを活用しましょう。
- 地理的リスクの再評価:自治体が作成するハザードマップを再確認するとともに、近年の気象データや災害データをもとに、自社拠点だけでなくサプライチェーン全体の地理的リスクを評価しましょう。
- サプライチェーン全体のレジリエンス評価:自社だけでなく、主要な取引先や物流網の災害脆弱性を把握し、代替ルートや複数ベンダー確保を検討しましょう。
具体的な例を挙げます。企業が国内外に新しい工場や物流拠点などを建設する際、その土地での自然災害の発生リスクは、最新の気象データを用い、気候変動シナリオに基づく今後の予測も加味して正しく評価する必要があります。地域によっては防災インフラが不十分なケースもあります。過去には、日本企業の海外工場が集中豪雨に見舞われ、原材料や部品調達が滞り、国内での商品製造にも支障をきたした例がありました。自然災害リスクを再評価した上で、災害級の自然現象が発生した場合の自社商品の売上への影響なども想定し、自社拠点の開発可否や規模などを決定することが重要です。
CSRとしての気候変動対策の取組
CSRとしての気候変動対策の指針も、近年整備が進んでいます。2023年1月に改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」では、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、サステナビリティ情報開示が義務化されました。さらに2025年3月には、サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準を公表し、そのテーマ別基準第2号が「気候関連開示基準」となっています。今後はこの基準に基づいた開示が義務化されます。その基準の中でも代表的なものが、GHG(温室効果ガス)排出量に関する詳細な開示や目標設定です。
これはお天気マーケティングとは少し毛色が異なる内容ですが、気候変動に関する企業の取組の方向性として欠かせないトピックです。
まとめ
ぜひもう一度、本連載を第一回から読み返していただき、BCPの内容を再検証し、直近の気候変動の状態に合わせてアップデートいただきたいと思います。「地球沸騰化」と呼ばれる状態は、少なくとも今後数十年は続くことでしょう。現在の二酸化炭素排出削減への取り組みが不十分な場合は、むしろ地球沸騰化はより加速度的に進むことも十分考えられます。短いスパンでの日々の気象変化から、長期的な気候変動まで、メーカー企業として取り組むべき課題は数多くあると思います。この連載がその一助になったとしたら、筆者としてもこの上ない幸いです。
※気象庁ホームページについて 気象庁ホームページで公開している情報は、誰でも、利用規約に従って自由に利用でき、商用利用も可能です。出典の記載等の注意事項は下記の規約をご確認ください。 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
〇「常盤勝美のお天気マーケティングブログ」過去記事はこちら https://www.truedata.co.jp/blog/category/weather_marketing
〇「メーカー企業のための気象&購買データ活用法」バックナンバーはこちら 第一回 「意外と知らない!?業務に使える気象データ3選」 第二回 「気象予報士が教える、長期予報の活用方法と行間の読み方」 第三回 「長期予報に基づく売上の予測値計算法」 第四回 「長期予報を活用したコストロスモデル」 第五回 「今後の日本の気候はどうなっていくのか?」 第六回 「大胆仮説!2050年の日本の天候」 第七回 「異常気象に備えるための心得とは」 第八回 「ウェザーMDを利用した商品開発」 第九回 「商品前線の活用」 第十回 「広告宣伝の効果と気象の影響の切り分け法」 第十一回 「メーカーの取り組むべき天候リスクヘッジ」
〇コンサルティング、講演・セミナーのご依頼、True Dataへのお問い合わせはこちら https://www.truedata.co.jp/contact 本稿の内容をもっと詳しく知りたい、自社の業務に落とし込んだ具体的な内容を聞きたいというご要望がありましたらお気軽にお問合せください!

株式会社True Data 流通気象コンサルタント 常盤 勝美
〈プロフィール〉
大学で地球科学を学び、民間の気象会社で約20年にわたりウェザーマーチャンダイジング関連サービスに従事。2018年6月、True Dataへ入社し、気象データマーケティングを推進。著書に『だからアイスは25℃を超えるとよく売れる』(商業界)など。気象予報士、健康気象アドバイザー。